こんにちは、こんばんは。オリーブです
今日はちまたでよく聞く
「公文式ってどうなの?」
「公文って教えてくれないんだよね?」
「発達障害があるけど、通えるのかな?」
という疑問に対し、現役の公文指導者がお答えします
合うor合わない?
まずは結論から言えば……
「合う子には合うし、合わない子には合わない」です
それを言っちゃあおしまいよ……みたいな回答ですがwww
でも、これが真実。
公文式に関わらずどんなメソッドもそうです
そしてそれは――
通常発達の子も
発達障害の子も
知的障害の子も
みんなそう
100%誰にでも合う教材やメソッドなんて存在しません
そんなものがあったら、その教材やメソッドだけが生き残り
競合は消えます
でも、世の中そうなってはいませんよね
つまり、どの教材やメソッドにもメリット・デメリットがあって
お子さんによって合う・合わないがあるわけです
なので、実際に無料体験などで試してみるのが一番だと思いますが
その前に――まずはメソッドについて知りたいって思いませんか?
その中でも、公文式ってどうなの?
についてお伝えしていきたいと思います
公文式の特徴
まずは、公文式が生まれた経緯をご存じでしょうか?
公文は元々、会長である公文公(くもんとおる)さんが
我が子のために始めたメソッドです
高校の数学教師だった会長は帰宅が遅く、我が子の勉強を見てあげられませんでした
(奥さんからは人んちの子ばかりじゃなく、自分の子も見てと言われていたそう)
そこで手製のプリントを用意し、奥さんに預けました
プリントは翌日、下校した息子さんに渡されます
息子さんは父親が書いた例題をヒントにプリントを解き、
その日のうちに母親に手渡します
母親を経由して届いたプリントを会長は夜遅くに採点し、
翌日のプリントを作成しました
つまり、公文式のメソッドは
「例題を見て考え、自力で解く」=自学自習
という考え方のもと、生まれた学習法なのです
その考え方は今でも続いています
例えば算数
初めて学ぶ単元には例題が配置され
一連の解答方法と答えが載っています
それを見てじっくり考え、答えにたどり着くまでの流れを確認し、
実際に問題を解きます
公文式は教えないの?
よく「公文は教えない」と言われます
半分当たってますが、半分は違います
「教えない」のではなく、「見守っている」が正解ですね
公文の学習には例題をよく観察し、考える時間が必要です
この考える時間に「教え込まない」というだけです
じっくり考えている子
分からなくてボンヤリしている子
見ればすぐにわかります
もちろん、ボンヤリしている子にはすぐに対応します
逆に、じっくり考えている子に
「これはね~」と話しかけるのはナンセンス
考えたのちに手が動くかどうか……
指導者は見て見ぬふりをしながら固唾を飲んで見守っています
どれくらいの時間見守るかは子ども次第
集中しているか、そうでないかでも変わりますし
これまでの理解度を考慮してタイミングを見計らいます
当然のことですが、全く分からなかった子には全部教えます
しかし全部教えなければ理解できない、ということは
これまでの学習が十分習熟していないかも、と疑います
場合によっては前の学習を復習することもあります
大抵の場合、部分的に理解できなかったところだけ説明すれば
その後は「あ! そっか!」といって子どもはスラスラ解き始めます
今まで手が止まっていたのが嘘みたいにドンドン解いていきます
こうやって言葉にしてみると、公文の学習は
自力で敵キャラを倒したり、アイティムを探したりしながら
クリアを目指す冒険型ゲームに近いかもしれません
ゲームにはあまり詳しくないですけど💦
マリオとかゼルダとかスマブラとか、
いきなり攻略本片手にやらないじゃないですか
最初はとにかくやり込みますよね
何回も「ゲームオーバー」を突き付けられて悔しがったりして。
どうにもクリアできなくなった時、攻略本の手を借りる
公文もそれと同じです
攻略本(指導者)は適切に状況を見極め、必要な情報だけを与える
子どもたちはネタバレ無しのアドバイスがもらえるわけです
なので、冒険型のゲームが好きなお子さんはハマればハマります
現に私の教室では、あまりに手が止まっているので見かねて声をかけると
「先生、ヒントちょっと待って! もう少しで分かりそう」
といって、『ヒント待て』を希望する子もいます
こういうお子さんはだいたいゲーム好き♪
特にマリオみたいに隠しアイティムとか、強い敵キャラがいる
ゲームが大好きなことが多いです
逆に合わない子は
アドバイスが聞けず自己流にこだわって
それでバツが付くとやる気が一気に下がる子
ですかね……
落ち込みが一時的なものなら全然いいのですが
ずっと引きずるとなると……公文は向かないですね
(公文に限らないかもしれないですが)
解答の流れを理解したうえで、自分のアレンジを加える子は
さらに賢くなる可能性を秘めています
しかし、最初からルール無視(計算のルールを守らない、音学習を蔑ろにする、問題をよく読まない)で自己流に走る子はバツになる可能性もアップしますし
その上モチベーションまで下がりっぱなしとなると
指導する側も「ルール守ってやろうよ…」としかいえません
ただしそれがASDの子だったり、健常だけど低年齢のお子さんの場合、
保護者の方が気持ちの切り替えを学ぶ良い機会だと思っていただけるなら
その限りではありません
もちろん保護者の方の協力は必須となりますが、
学力だけでなく自立の練習として
公文を選ぶというのはアリだと思いますす
話が少しそれてしまいましたが
大抵の場合、一から十まで教え込まなくても
子どもは自力で考えて答えを出そうとします
(教材もそうできるように作られています)
大人になればいつでもどこでも、教えてくれる先生がいるわけではありません
自分で調べて、考えて、自分なりの答えを導き出さなくてはいけません
公文式で学ぶということは「自己決定」の練習でもあるのです
「教えない」のではなく、
「教えられなくでも自分で考える子」になって欲しいのです
それから、あと一つ忘れてはいけないのは
もし考えても分からなかった時に、自分から
「教えて」
と言える力もつけたい、と指導者は思っています
分からないことが恥だと思ってほしくないのです
「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」とはよく言ったものですが
分からないことを分からないままにしない
ということも、私達指導者の役目です
もちろん、恥ずかしがり屋でなかなか言い出せない子でも
少しずつスモールステップで自分の気持ちを伝えられるよう
指導者は配慮します
(場面緘黙の子も同様です)
声が出せなくても、先生と目が合った時に
小さくうなずく
小さく手を上げる
そっと手招きをする
「おしえて・わからない」などと書かれたカード見せる
そんな小さな「伝える」から、
いずれ(どんな形ででも)自分で質問が出来る力を
つけていけるよう日々試行錯誤をしています
そんなわけで、
「公文は教えないのか?」と聞かれたら
「はい、そこからたくさんのことを学ぶために
すぐに教えることはしません」
と、私なら答えます
多動な子は学習できるのか?
ADHDやASDがある子は学習できるか、といわれると
これについては「教室による」とお答えします
公文の先生としての目線でも書いた通り
公文式はフランチャイズですから、先生によって得手不得手が違います
幼児教育が得意な先生
英語指導が得意な先生
などなど、実に多種多様です
なぜなら、先生方にはそれぞれ違ったバックグラウンドがあるから。
大学の英語科を出ている先生に理系の先生は敵わないですし
保育士のご経験がある方とそうでない方では、だいぶ違いがあります
学校の先生だっていろんな方がらっしゃるでしょう
低学年が得意な先生とか
高学年が得意な先生とか
外で一緒に遊んでくれる先生がいたり、
教室で読み聞かせをたくさんしてくれる先生がいたり。
先生も指導者も人間ですから得意不得意も当然違います
私はたまたま、障害児教育を専門に学んだ経験があり
我が子に発達障害があったり
公文の仕事以外にも放デイで児童指導員をしていたりと
障害を持つお子さんと関わることが多かったので
自教室であれば対応可能であるとお伝えしています
また、最近公文教室ではKC(公文コネクト)を導入している教室が増えてきました
KCというのは公文のタブレット学習のことを指します
紙の教材ではなく、タブレットで学習できるため
物理的な宿題交換も無くなり
今まで指導者から伝えられていた習熟具合も
タブレットでいつでも確認できます
また、宿題分の採点が翌日には出来ているので(教室によります)
自宅でお直しができますし、記憶が新しいうちにお直しができる
というメリットもあります
これをzoomと組み合わせることで、オンライン学習も可能です
多動で教室を歩き回ってしまうんじゃないか
他の生徒さんに迷惑をかけてしまうんじゃないか
聴覚過敏や臭覚過敏があって教室にいるのが苦痛
というご心配がある場合
zoom+タブレット学習を使って、自宅で学習することも可能です
ちなみに、zoomはお子さんの学習の様子を見たり
手元の様子を映して必要な声掛けをしたりするのに使います
(背景をぼかすことも出来るので「家の中が丸見え~💦」という心配はいりません)
もちろん、オンライン学習やタブレット学習は
障害の有る・無しに関わらず利用できます
冬場は雪で通うのが大変
引越ししたら教室が遠くなった
週に2回の送迎は大変💦せめて1回になれば…
などの理由でもご利用いただけます
(紙の教材を学習している生徒さんも利用できます)
ただし、オンライン学習もKC(公文コネクト)も
導入されている教室とそうでない教室があるので
ご興味ある方はお近くの教室にお問い合わせください
まとめ
今日は「公文式ってどうなの?」
ということについていろいろお話しました
・どのメソッドにも合う・合わないがある
・発達障害があっても無くても、合う・合わないは同じ
・公文式は「テストの点数を上げること」の他に、「生きる力」をつけるところである
・通室が難しいと感じたら――オンライン学習も可能(対応できる教室を探す)
など、お話させていただきました
受験や学力重視であれば、公文式でなくてもいいと思います
学力+生きる力をつけさせたいのであれば
一度公文式教室を見に来ていただければと思います
塾選びの参考にしてください

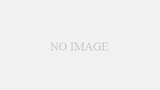
コメント