こんにちは、こんばんは
現役公文式指導者&放デイ児童指導員
三姉妹のママでもあるオリーブです
今日は20年に渡る子育ての中で
ちょっと厳しすぎたかな……
と、反省している
「長女の学習指導」についてお話します
初めての子育ての中、紆余曲折あって
私は公文式の指導者になることを選びました
母親としてだけでなく
指導者として経験を積む意味でも
長女の指導は悩みに悩みました
研修で学んだことをフル回転して
基本に忠実
迷ったら進める
やってみよう、やってみなければ分からない
を合言葉に
いろいろ試していました
それゆえ、良かったところ・反省すべきところ
たくさんあります
今日はその中から
いくつかをご紹介したいと思います
一生懸命になり過ぎた
私が公文式指導者になったとき
長女は年中さん
次女は生後9か月でした
当時の長女はひらがながあまり読めませんでした
どれくらいのレベルかというと――
「あるところに いっぴきのかわいいウサギが――」
と、本に書かれていても
「ありさんの『あ』、ルビーの『る』、トマトの『と』……」
という感じで、
使っていたひらがなの表の
イラストと一緒に文字を覚えていて
お話を読むというより
文字を拾って読んでいるだけでした
当然のことながら、
この本がどんなお話なのかは
ひとり読みでは分かりません
指導者になったとき、
この子がどれくらいの期間で
文字が読めるようになるのだろうと
楽しみでもあり、
指導者としてしっかり導けるのかと
不安でもありました
しかし、公文式でつけられる力は
将来の生きる力
研修で教わったことをフルに活かし、
基本に忠実に
長女の様子や完成時間を元に
教材を進めていきました
学習習慣がつくまで…が苦悩の始まり
幼児期は決まった時間に
「公文タイム」を設けることで
学習習慣が付きやすい
そう研修で習った私は幼稚園から帰宅後、
おやつを食べてひと休みした後に「
公文タイム」を設けました
始めたばかりの頃は
(学習習慣や作業力をつけることが目的でもあるので)
教材は易しく、本人も楽しそうです
1週間・1か月と続けるうちに長女も習慣になり、
少しずつですが机に向かう習慣がつきました
でもね、そこは幼児さん😖
気分のムラが大きいんですよ……
この時もう少し臨機応変に対応できれば
良かったなぁ、と。
相手は4歳
完璧を求めちゃダメですよね💦
しかしこの頃の私ときたら
「ま、いっか」って思えなくて……
グズる長女を怒ったりなだめたり
ありとあらゆる手を使って
机に向かわせていました
本当、ゴメンって感じです
粘り強さが仇になる
やがて、本人の能力相当のところまで追いつくと
これまでよりは時間がかかるようになりました
ここで、本来なら宿題量の調整を
すべきだったんだと思います
ただ、ひとつだけ言い訳をすると
幼児期の子どもって集中力にムラがあり
同じくらいの難易度でも
気分の乗る・乗らないでかかる時間が
大幅に違います
経験の浅い私は、そのあたりを考慮して
宿題を組むということができず
常に同じ量の宿題を長女に渡していました
しかも、ここ数か月で
(本人の性格もあるのですが)
メキメキと学習能力よりも(笑)
粘り強さを手に入れていた長女は
1時間でも2時間でも、机に向かって
作業が出来るようになっていました
集中は……していなかったでしょうけど💦
その粘り強さは日を追うごとに強化され
気付けば半日でも座っていられるように!
おかげで週末のお休みの日
朝一番で公文に取り掛かるのが
我が家のルールだったのですが
半日かかって終わらせるため
お出かけはいつも昼過ぎになるという……
(下手すると夕方とか😖)
ホント、なんでこの時に
宿題量の見直しをしなかったんだろう
と思いますよね
でも、研修では
「できるだけ10枚学習を推奨」とあったんです
作業力や集中力、学習習慣のためにも!
もちろん、個人別に枚数調整して良い
とされています
この個人別というのがなかなかの曲者で
経験値の無い私には
どの程度の状態でどれくらい調整するかが
まったく分かっていなかった
我が子だから、というのもあって
多少無理を承知で、という思いも
少なからずありましたけどね
おかげで長女は3教科全て
小学生J教材(高校教材)となりました
が、
いつの間にか
「公文タイム」は「苦悶タイム」に……!
学習する長女も
やらせる親の私も
苦しい時間となっていました
反省を活かして
長女が小4になる頃には
私自身の経験値も少しずつ増え、
宿題の調整を柔軟に行えるように
なっていました
長女で培った経験は
現在通ってくれている生徒さんや
次女、三女にも活かされています
指導者としては「ここまでやって欲しいな」
と思うところもありますが、
子を公文に通わせている親の気持ちも
(十分すぎるほど)分かるので
宿題はわりとゆるめ~に組んでいます
というのも、生徒さんたちの
「やった!できた!」
「最後までやり通せた!」
「宿題を全部持ってこれた!」
という気持ちを大切にしたいから
(希望があればそれに沿うように出しますが)
それでも、うちの教室では
2学年先、3学年先に進んでいる子が半数以上
宿題が少ない分、教室での枚数を「頑張れる枚数」にするってことと
渡した宿題は9割の子が全部やってくるってことが主な要因かな
やっぱりモチベーションって大切です
大人になった長女は
そんなわけで、三姉妹の中では特に厳しく
学習指導をした長女ですが……
この春、都内の大手企業に就職し
社会人として働いています
先日帰省した際に
こんなことを聞いてみました
「春から社会人になったけど、公文やっててどうだった?
少しは役に立ったのかな?」
長女はなんて答えたと思います?
私は恨み節が炸裂すると思っていました(笑)
「確かにママは厳しかったし、宿題も多かったから大変だったけど
『粘り強さ』とか、『練習すれば必ずできるようになる』っていう
謎の『自信』がついたのは公文のおかげだと思ってる
未知なるものへの『挑戦心』も、公文のおかげかな
学校の授業も楽だったし、今は感謝しかないよ
ママ、私に公文やらせてくれてありがとうね
将来自分に子どもができたら、絶対に公文やらせるよ」
思わず泣いちゃいましたよ
反省点はいっぱいあるし
もっとこうしてあげればよかった
ああしてあげればよかった
今になって思うことがたくさんあります
経験不足ゆえに
長女には辛い思いをさせたはず
「あなたのためよ」と言ったことは無いけれど
「親が居なくなった後でも、自立できる人間に」
という話はよくしてたかもしれない
思いは伝わっていたのかな
反省しかない子育てや指導も
子どもが大人になって
こんなふうに言ってもらえて
ああ、公文の指導者やっててよかったな
と思うとともに、
通ってくれているすべての子に
そう思ってもらえるように
これからも頑張らなきゃ
と、決意を新たにしました
まとめ
子どもが1才なら
親も子育て1年生
親も子も、全てが手探り状態なわけです
時には失敗もあるし
後になって猛省することもあるでしょう
(私はいつもコレ)
でもね、私思うんです
一生懸命子どもと向き合った結果なら
子どもはちゃんと思いを受け止めてくれる
そのときは分からなくても
彼ら彼女らが大人になったとき
「パパが、ママが言ってたことはこれか!」
って思う時がきっとくるんです
このところ次女もね
「昔ママが言ってたことってこれか、って思うこと
最近多いんだよね」
って言ってきます
「あの時は『うるさいな~』って思ってたけど(笑)」
って追加で言われるけどww
その時は幼くてわからなくても
繰り返し繰り返し伝えたことは
ちゃんと子どもの中に残っていて
ある時ふと、「ああ、このことだったのか」
って気付いてくれる
それって嬉しいですよね
思いはいつか伝わります
親は「幼いから分からないだろう」ではなく
いつかきっと分かる日が来ると思って
伝え続けることが大切ですね
学習だけでなく
マナーやルール
思いやり 等々
一本筋を通して伝え続ける
これが親の役目なのかもしれませんね

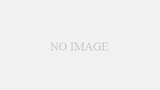
コメント