こんにちは、こんばんは
放デイの児童指導員&公文の指導者
そして自身も二人のADHDっ子を育てるオリーブです
子どもの服薬は悩ましい問題ですよね
飲ませるかどうかを、本人ではなく親が決断しなければならない
本当に難しいところです
今回は母として、私が娘たちに服薬という決断をした過程と
児童指導員として、服薬を決断する目安的なものをお話したいと思います
普通の生活ができない
次女がADHDと診断された過程については以前に書いた
次女がADHDと診断されるまで
の通りです
とにかく幼少期から目が離せない子でした
迷子なんて日常茶飯事
何にでも興味を示すわりに、すぐに飽きて次の興味へ……
売り物だろうが何だろうが手あたり次第触ったりいじったり
不注意優位型ということもありケガも絶えません
とにかく目が離せないので、買い物も家事もままならない状態でした
しかし我が家には「目が離せない」ことよりも
さらに深刻な問題があったんです
それは次女が「眠り過ぎる」ということ
朝も起きれず、遅刻常習犯
学校でも常に眠い
帰宅すればすぐにバタンキュー!
宿題どころか、夕飯になってもお風呂の時間になっても起きれない
無理やり起こして入浴させればお風呂で寝てる……
乳幼児の頃は「よく寝る子」で済んでいましたけど
さすがにこれは異常だと思いました
いよいよ高学年になっても生活は酷くなる一方で
学校へも行けなくなりました
そこでも紆余曲折ありましたが、ようやく本人もこれじゃあマズイ…と思ったのか
重い腰を上げ受診へと至ったわけです
診断結果を踏まえて
小児の発達外来がある病院で
「ADHD」の疑いありと診断されました
そこでは私たち親子の困りごとについて
よく話を聞いてくださいました
「睡眠障害」についても、ここで詳しく説明をされ
ADHDと睡眠障害には密接な関係があること、
症状改善のために「服薬」という選択肢があることも
ドクターは丁寧に教えてくれました
提示された薬は「コンサータ」
ADHDの治療薬として2007年12月に発売された薬です
脳内の伝達部室の働きを活性化することで
集中力や注意力を高め
衝動性や多動性を改善する効果が期待できます
ただし、副作用として依存リスクがあること
食欲不振や吐き気、嘔吐、不眠、体重減少などがあることを説明されました
ドクターがコンサータを勧めた理由は
この薬に覚醒作用があること
常に眠くて眠くて仕方がない次女にはうってつけでした
ただ、ドクターに勧められたからと言って
すぐに娘に飲ませるかと言われたら、即答はできません
脳の中枢神経に作用して精神機能に影響を与えるということは
コンサータは「向精神薬」だということ
十代前半の娘に飲ませて大丈夫なんだろうか、と不安になりました
それについても、ドクターは丁寧に説明してくださいました
依存性については用法容量を守れば問題ないこと
体重減少や食欲不振については月1回の受診でしっかり管理していくこと
など、ひとつひとつ不安材料を潰してくださいました
なにより、話を聞いていく中で
薬の副作用よりも、生活がままならないことの方が
深刻であると気付かされました
人として生きていくために必要な、食事や入浴ができない
すでに不登校気味となり、学校へ行きづらさを感じている
手をこまねいている暇はないと思いました
私の中では「服薬」という一択しかありませんでした
このとき、次女は中学2年生
そろそろ自分のことは自分で判断してもいいだろうと思い、
私自身は答えをすぐに口に出しませんでした
次女も同席して話を聞いていたので、情報量は私と同じ
ドクターも、まずは本人にどうするか訊ねてくれました
次女の決断は「薬を飲みたい」
学校で眠いのがツライ
学校にいけないのが悲しい
やりたいことが眠くてできないのが苦しい
それが少しでも良くなるなら薬を飲みたい
ドクターにはっきりと言うことができました
私は本人の意思を尊重します、とお答えしました
親が決断しなければならないときは…
我が家の場合は次女の年齢が大きかったので
本人の意思を聞くことが出来ました
しかし、もっと年齢が小さかったら
親が判断しなければいけません
現に今、決断を迫られている方も
いるかもしれません
「どうしていいか分からない!」
という方のために
服薬を決断するための目安を
お伝えできればと思います
あくまで私(経験者+一児童指導員)の見解です
参考程度に考えていただければ……
と、その前に。大前提として……
ADHDやASDなどの発達系の障害は現状で治ることはありません
肌の色や瞳の色、髪質と同じように持って生まれた特性です
その特性と一生付き合っていかなくてはならないことだけ、
頭に入れておいてください
それを踏まえたうえで考えてみましょう
①命の危険があるかどうか
多動性や衝動性が強い子は
飛び出しなどの危険行為が多くあります
知能が高い子であっても
その衝動性を押さえることは難しいといいます
(頭でわかってても体が勝手に動いてしまうから)
もし飛び出しそうになったら
大人は手を掴んだり体を押さえたりして
ストップをかけます
放デイなどでも社会経験などで
事業所の外へ出ることがあるのですが
突発的な動きに対応できるよう
常に気を張っていますし
そういった思わぬ事故を回避するため、
事前に職員の数やルートを考えます
それくらい、バッと衝動的に動く相手を止めるのは
力も神経も使います
このように、力も神経も使う支援を
一生やり続けられるのだろうか?
と考えてみてください
大きくなれば子どもの力も強くなる
逆に親は年をとって力が弱くなる
そして間違いなく、親の方が先にいなくなる
親亡き後、支援を引き継ぐ人たちにも
同じ試練を課せられるのか?――
どうでしょうか? 想像できましたか?
衝動性が強く、どうやったら命を守れるのか……
そう考えることが多くあるのなら
「服薬」という選択肢もありなのでは、と個人的には思います
副作用や依存性を心配する気持ちも、親としてとても分かりますが
それは命あってこその心配
まずは命を守るために出来ることをは何か、を考えるべきかと思います
その中の一つに「服薬」という選択肢を加えても間違いではないと思うのです
②将来的な自立の妨げになっていないか
うちの子はこれに該当していました
「睡眠障害」を何とかしなければ
将来的な自立を促せないと判断し
服薬という決断をしました
これと同じように例えば……
多動のためイスに座っていられない・集中もできない
という子がいたとしましょう
この特性によって何が起きるかというと
学習障害などの特性がないにも関わらず
多動という特性のために二次的な学習障害を
併発する可能性が出てきてしまうのです
現在の日本の制度では、18歳を過ぎると
支援の手は薄くなります(18歳の壁と言われています)
この時に簡単な読み書き・計算ができるか
コミュニケーション能力があるかによって
学校卒業後の進路(就職等)に大きくかかわってきます
障害者就労支援などを利用した場合は
サポート支援が必要になればなるほど
手に入るお金は少なくなります
例えば…
就労継続支援A型の場合、平均給与は
月額8万3千円ほど(厚生労働省の調査による)
就労継続支援B型の場合、「給与」ではなく
「手当て」になるのでそれよりも少なくなります
薬への過度な期待は禁物ですが
服薬によってわずかな時間でも座って集中できるのであれば
将来の選択肢を増やすことにもつながります
親亡き後も、自立した生活を送るために
自立の妨げになっていないだろうか
という目線で判断するのもアリかなと思います
悩むことこそ親心
ひとつ、二つの例だけで判断するのは難しいですね
発達障害と一口にっても十人十色
障害の出方や併発具合も違います
こうだから、とか
ああだから、とかで
決めることはできません
だからこそ、子どものことをよく知っている親が
たくさん悩んで、考えて、決断した答えで良いと思うんです
ただ、世間体とか親の好き嫌い(私は薬に頼るのがキライ)などで
判断してはならない、ということだけです
ドクターと薬についてトコトン話をして
パートナーなど信頼できる方ともたくさん相談して
ご自身が納得できることが一番大事
そして将来、その決断について
子どもにきちんと説明できる
そういう決断をしてほしいな、と思います
服薬についてまとめ
服薬を始めるか否か、その決断は容易ではないこと
もし検討するならば
①命の危険があるかどうか
②将来的な自立を妨げていないか
まずはこの二つに焦点を当てて
考えると答えが見つけやすい
服薬をするにしても、しないにしても
親がたくさん考え悩み、その決断を
子どもに説明できることが大事
以上のことをお話させていただきました
もちろん私の個人的な見解ですので
合う合わないあると思います
この考え方がすべてではないですし
もっといい方法があるかもしれない
ただ、私自身も悩み苦しみながら通った道
今現在決断を迫られている方にとって
何かしらのヒントになれば嬉しいです

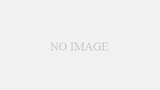
コメント